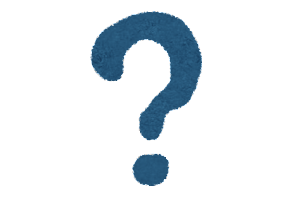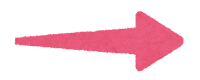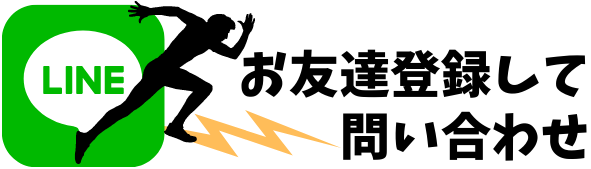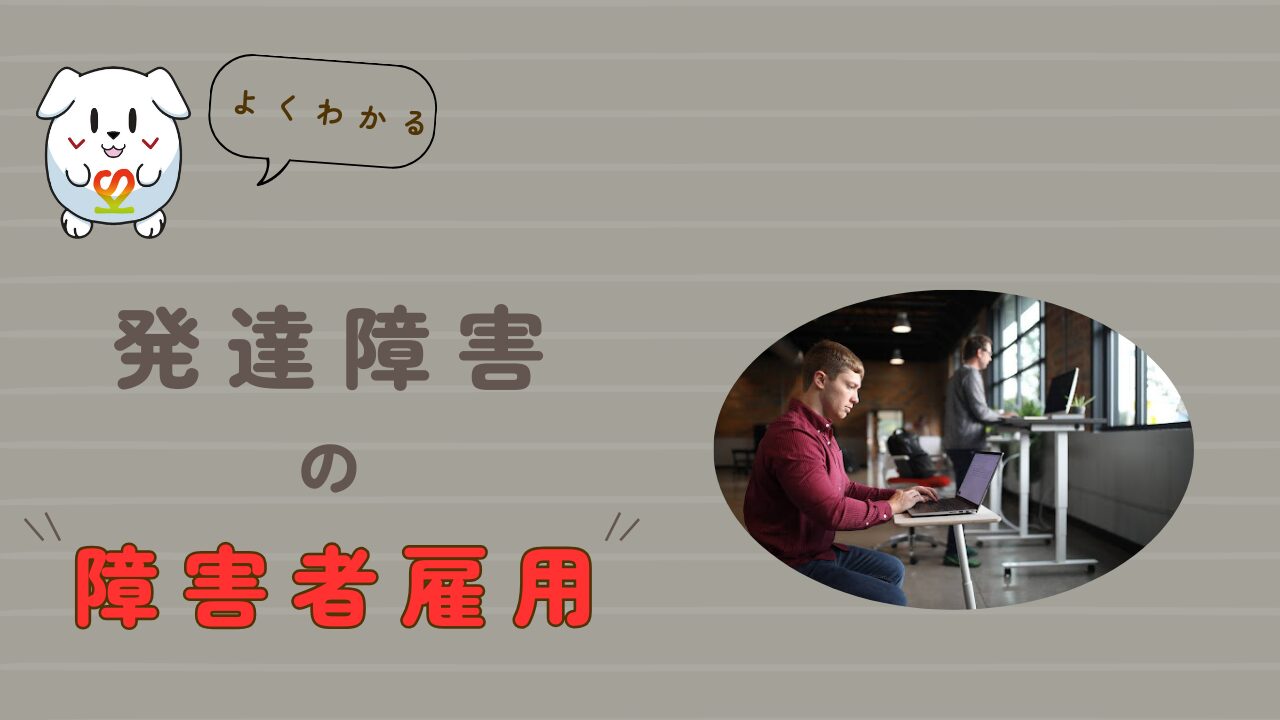発達障害のある方で、就労を希望しているものの、障害者の働き方についてよく分からずにいる人も多いのでは?
そこでこの記事では、発達障害のある方に向けて、障害者の雇用を分かりやすく解説します。
障害者の働き方は、大きく分けると「一般就労」と「福祉的就労」に分けられます。
さらに、一般就労は「障害者雇用」と「一般雇用」に分けられます。
福祉的就労とは、就労継続支援A・B型事業所などでの就労です。
この記事では、最初に発達障害の特性と困り事を取り上げた後、障害者雇用と一般雇用について解説します。次に障害者の就労を支える「合理的配慮」を紹介。終わりの方では障害者の就労に関わる相談先もご案内します。

この記事を読むことで、発達障害者の働き方への理解がワンステップ進みます!!
最後までお読みいただければ、障害者の就労サポートの相談先も分かります。
発達障害とは
発達障害とは、生まれつき脳の機能の一部に偏りがあることによって、対人関係やコミュニケーション、行動や感情のコントロール、仕事や学業などに大きな困難を伴う状態のことです。主な診断名として、ADHD(注意欠如多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などがあります。
以下、3つの診断名の特性と困り事を解説します。
ADHD(注意欠如多動症)
[特性]
多動性(過活動)や衝動性、不注意を症状の特徴とします。
これら3つの特徴をもとに、不注意優勢型、多動性・衝動性優勢型、混合型の3つの診断タイプに分類されます。
[困り事]
忘れ物が多い。しゃべり過ぎてしまう。衝動的に行動してしまう。
ASD(自閉スペクトラム症)
[特性]
適切なコミュニケーションが取れず、対人関係での難しさを抱えやすい面があります。また、ある特定のモノや場所に強いこだわりや固執、興味を持つことがあります。
[困り事]
相手の感情や表情を読み取れない。自分のやり方やルールに固執する。
LD(学習障害)
[特性]
知的発達の遅れがないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」などの能力に困難が生じます。読みにくさや書きにくさなどの程度や現れ方は人によりさまざまです。1つの能力だけに症状が出る人もいれば、複数の能力に症状が出る人もいます。
[困り事]
文字や行を読み飛ばす。うまく文字を書き写せない。数の大小が分からない。
※ADHDとASDを合併する場合も多くあります。
※発達障害の「二次障害」とは、発達障害の傾向や特性に伴って発生する精神障害やうつ病などの二次的な困難や問題のことです。
障害者雇用って何?
「障害者雇用」とは、障害者一人ひとりがその特性に合わせた働き方ができるように、行政や企業などが特別に障害者雇用枠を設定して障害のある人を雇用することです。
障害者の雇用については「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」により定められています。
この法律の目的は、障害のある人が障害のない人と同じように、その能力と適性にもとづいて職業につき、自立した生活を送れるようにすることです。
さらに大きな理念として、障害のある人が障害のない人とともに生きる「共生社会の実現」を掲げています。
また、障害者が仕事をする際に生じるさまざまな支障を改善するために、事業主には障害者に対する「差別禁止」や「合理的配慮の提供」を義務づけています。
※障害者雇用では、応募条件として障害者手帳の所持が必要です。
一般雇用って何?
「一般雇用」とは、誰でも応募できる「一般の採用枠」で雇用することです。そのため障害者は、障害のない人と同様の条件で働くことになり、障害のない人と同じ水準の仕事を求められます。
その代わり、一般雇用は障害者雇用に比べて、職種の幅が広く求人数も多いため、障害者雇用よりも希望する仕事を探しやすいといえます。就職後は、昇進や昇給が期待できるでしょう。
一般雇用では、障害のあることを企業側へ伝えるかどうかは障害者本人しだいです。障害を開示する就労を「オープン就労」、障害を開示しない就労を「クローズ就労」といいます。
クローズ就労では、障害に対する配慮をほとんど望めません。また、一般雇用枠のオープン就労であっても、障害者雇用に比べると障害への理解や配慮は十分とはいえません。そのため、一般雇用での障害者の早期離職が多くなっています。
※一般雇用のオープン就労で、どの程度の理解や配慮が得られるかは、企業や職場の上司により異なります。就職前にしっかり見極めることが大切です。
職場の合理的配慮について
障害者雇用促進法では、障害者雇用率制度のほか、障害者に対する「差別禁止」や「合理的配慮の提供」を行政や企業などに義務づけています。
【合理的配慮とは】
合理的配慮とは、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するように、個別の対応や支援を行うことです。
行政や企業などには合理的配慮を示すことが求められます。ただし、合理的配慮の提供が事業主に対して過重な負担を及ぼす場合は除かれます。
[合理的配慮の例]
・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成する。
・発達障害がある方に対し、出退勤時刻、休暇、休憩に関し、通院や体調に配慮する。
【合理的配慮の流れ】
発達障害など、外から見ただけではどのような支障があって、どのような配慮が必要なのか簡単にはわかりません。障害者一人ひとりの状態や職場環境などにより、求められる配慮は多様で個別性が高いものとなります。そのため、具体的な配慮の仕方を障害者と事業者の間でよく話し合う必要があります。
以下、合理的配慮の流れを紹介します。
①事業者は障害者へ、合理的配慮の提供の申し出を呼びかけます。
②障害者は、業務上どのような支障があり、どのような配慮が必要なのか、希望するサポートを自ら申し出ることが大切です。
③障害者と事業者は、丁寧に話し合いを進めながら配慮の内容を決定します。
必ずしも障害者の要求通りになるわけではありませんが、できるだけ障害者の求めに応じる方向で配慮の内容が決められます。
【合理的配慮を伝える】
合理的配慮を求める際、障害者は今まで受けてきた配慮や支援の実績があれば、そのことを事業者側に伝えましょう。
適切な配慮を求めるためには自己理解が大切です。就労移行支援事業所などで自己分析や得意・不得意をまとめたものがあれば活用しましょう。
自分から合理的配慮を求めることを重荷に感じる方は、就労支援機関などのスタッフに援助を求めましょう。
相談はどこでする?
就労するにあたり、就労支援機関とのつながりは障害者の大きな支えとなります。
就労したものの、想像以上に仕事がたいへんだったり、体調管理が難しかったり、場合によっては理不尽な要求を強いられることがあるかも知れません。そのような時には、支援機関とのつながりが役に立ちます。
以下、支援機関を紹介します。
ハローワーク
ハローワークは公共の職業紹介窓口です。障害者枠と一般枠、どちらの求人も探せます。
障害の専門的知識をもつ相談員が、仕事に関する相談や情報提供に応じます。
※求職者登録(障害者登録)をする場合は、障害者手帳や医師の意見書などが必要です。
地域障害者職業センター
障害者が仕事について相談したり助言を受けたりするところです。
障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価や就職前の職業準備訓練、就職後の職場適応訓練などを実施します。
障害者就業・生活支援センター
障害者の「就業の支援」と「生活の支援」を一体的にするところです。
就業とそれに伴う日常生活での援助を必要とする人が、安定して自立した職業生活を送れるように支援します。その際、窓口での相談や家庭訪問、職場訪問など、関係機関と連携しながらサポートします。
発達障害者支援センター
就労支援としては、就労を希望する発達障害者に対して、就労に関する相談に応じると共に、ハローワークなどと連携して情報提供を行います。
必要に応じて、センターの職員が就労先を訪問して、障害特性や就業適性に関する助言を行うほか、作業工程や環境の調整などを行うこともあります。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所では、一般企業への就職を希望する障害のある方を対象に、一定期間、作業や実習の機会を提供して就労に必要な訓練・指導を行います。就職後6か月間、職場定着の支援も行います。
就労定着支援では、一般就労に移行した人を対象に、就労にともなう生活面の課題に対応するための支援を受けられます。
支援機関とのつながりがあれば、就職前でも後でも、専門知識をもつスタッフがあなたをサポートしてくれます。
まとめ
この記事では、発達障害の特性や困り事について説明した後、障害者雇用とは何か、一般雇用とはどのようなものか解説しました。また、障害者の合理的配慮を説明し、障害者の雇用に関わる代表的な相談先を紹介しました。
「発達障害のある私だけど、自分に合った仕事や職場を見つけて働きたい!」「障害者雇用を考えているけど、どこから始めたらいいの?」などと、就労に向け、最初の一歩を踏み出そうとしているなら、ぜひ一度、ケイエスガードをお訪ねください。
ケイエスガードは神奈川県川崎市にある就労継続支援B型・就労移行支援の事業所です。
ケイエスガードでは、得意を活かした就労をサポートするのが得意です!もちろん、利用する方のペースを第一に考える支援機関です!
興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。電話やメールでも大丈夫ですよ。