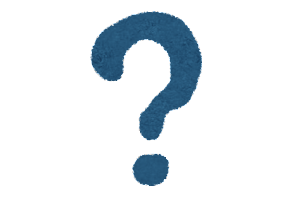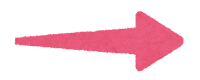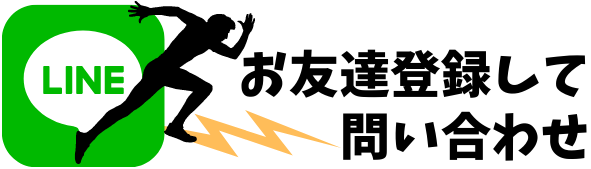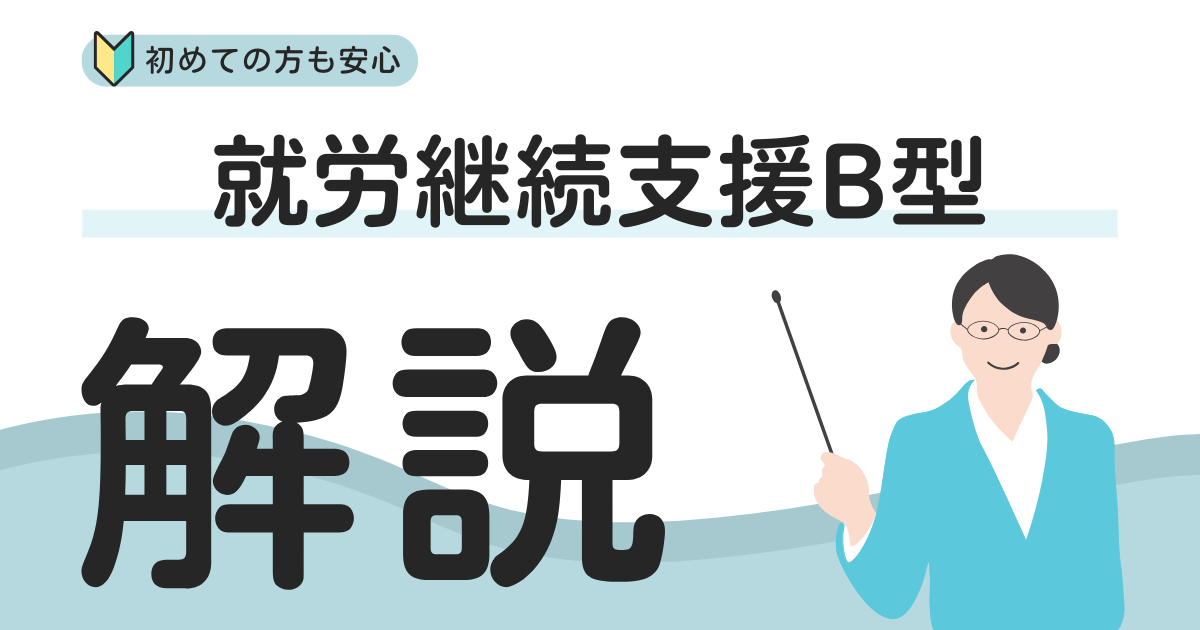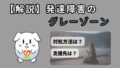障害のある方が就労を希望する際、障害福祉サービスやハローワークなど、多様な支援制度や支援機関を利用できます。そこで今回は、障害福祉サービスの中でも、「就労継続支援B型」というサービスを紹介しましょう。
この記事では、初めに就労継続支援B型の基本的な内容を解説します。次に、どんな人が就労継続支援B型の事業所を利用していて、どんな仕事をしているのか紹介します。利用者の一日の流れについてもご紹介します。
最後に、就労継続支援B型を利用するにはどんなステップを踏めばいいのか、手続きの流れも解説しました。

この記事を読めば、就労継続支援B型についての基本情報と利用の仕方が分かります。
この記事を最後まで読む、事業所で仕事に熱中するあなたの姿を、きっと想像することでしょう!
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、障害や難病がある人で、一般企業で働くことが困難な方の就労を支援する障害福祉サービスです。生産活動などの機会の提供、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つです。
就労継続支援はA型(雇用型)とB型(非雇用型)に分けられ、A型は事業所と利用者との間で雇用契約を結びます。B型は雇用契約を結びませんが、生産活動の対価として「工賃」を受け取ることができます。B型事業所の工賃だけで生活する額は稼げませんが、B型事業所は障害者の居場所あるいは働く場としての役割が強く、障害者の社会的孤立を防ぎます。
就労継続支援B型の利用によって、生産活動や就労に必要な知識・能力が高まった人は、就労継続支援A型や一般就労へと移行する道が開けます。
就労継続支援B型の対象者はどんな人?
就労継続支援B型の対象者となる人は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病のある方で、下記にあげる条件の内、いずれかを満たす人です。
① 企業等や就労継続支援A型での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者。
② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者。
③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者。
出典:厚生労働省「就労継続支援B型に係る報酬・基準について」
※特別支援学校の学生が、卒業後すぐに就労継続支援B型の利用を希望する場合、在学中に就労移行支援事業者などによる就労アセスメントを受ける必要があります。
※就労継続支援B型の利用に年齢制限はありません。利用期間にも制限はありません。
※就労継続支援B型のサービスを利用するには、基本的に障害者手帳が必要です。障害者手帳のない方が、就労継続支援B型を利用したい場合、診断書(又は意見書)の作成を主治医に依頼しましょう。診断書があることで、市区町村から障害福祉サービス受給者証が発行され、就労継続支援B型の利用が可能となります。
ただし、市区町村ごとに対応が異なる場合があり、事前に市区町村の障害福祉の担当窓口で確認しましょう。
就労継続支援B型の仕事内容
就労継続支援B型の事業所では、利用者の障害の状況・程度、体調やペースに配慮した生産活動や就労訓練が行われます。仕事内容は事業所によりさまざまですが、いずれも軽作業が中心です。
例えば、仕事内容は以下のようなものです。
・清掃作業
・農作業
・組み立てや梱包作業
・パソコンのデータ入力作業
・パンやお菓子などの製造や販売
・袋詰めやラベル張り
・チラシ折りやポスティング作業
・ミシン作業や手工芸
・カフェやレストランの接客や調理 など
農作業や清掃作業など、軽く体を動かす仕事。カフェやレストランなどで接客対応をする仕事。パンやお菓子などの物作りに関わる仕事。
上記のように、福祉的就労として馴染み深い仕事を行う事業所がある一方、最近ではパソコンを使う仕事ができる事業所も増えています。
例えば、データ入力を初めとして、動画編集やアニメ・ゲーム制作などが行える事業所もあります。
【勤務時間と日数】
就労継続支援B型では雇用契約を結ばないため、勤務時間や日数の定めは特にありません。そのため、利用者ごとの事情に応じて、勤務時間や日数を柔軟に調整することができます。
※事業所によっては、最低利用日数など独自のルールのある場合があります。
B型事業所の一日の流れ
就労継続支援B型事業所での一日の流れ(スケジュール)は、勤務形態の違いと利用者それぞれの利用状況により変わってきます。
勤務形態には「事業所内就労」「施設外就労」「在宅就労」の3種類があります。それぞれ就労場所や環境が異なるため、利用者の一日の流れは違うものになります。
・「事業所内就労」では、利用者は就労継続支援B型の事業所内で仕事をします。
・「施設外就労」では、事業所と契約を交わす企業まで利用者が出向いて仕事をします。
・「在宅就労」では、利用者は事業所に出かけることなく、自分の家で仕事をします。
就労継続支援B型事業所では、利用者の障害の状況や支援ニーズに合わせてスケジュールを柔軟に変更できます。そのため、勤務形態の違いに加えて、障害やニーズ、体調などにより、一日の流れは利用者ごとに変わってきます。
例えば、週に三日通い、日に3時間だけ利用することもできますし、毎日通って一日フルに働くこともできます。
※就労継続支援B型事業所の始業・終業時間、一日の就労時間の設定は、事業所ごとに異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
以下、あるB型事業所の「事業所内就労」と「施設外就労」の一日の流れです。
【例:「事業所内就労」の一日の流れ】
・10時までに出勤
・10時00分 朝のミーティング、体調のチェック
・10時15分 組立て作業開始
・11時00分 休憩
・11時15分 組立て作業再開
・12時00分 片付け、昼食準備
・12時15分 昼食
・13時00分 パソコンの入力作業開始
・14時00分 休憩
・14時15分 パソコンの入力作業再開
・15時45分 片付け、掃除
・16時15分 一日の振り返り、帰宅
【例:「施設外就労」の一日の流れ】
・10時までに出勤
・10時00分 朝のミーティング、体調のチェック
・10時15分 車で移動
・10時30分 清掃作業開始
・12時00分 車で移動
・12時15分 昼食
・13時00分 車で移動
・13時15分 農作業開始
・14時15分 休憩
・14時30分 農作業再開
・15時45分 片付け、車で移動
・16時15分 一日の振り返り、帰宅
利用手続きについて
就労継続支援B型を利用するための手続きの流れ(①~④)を紹介します。
①就労継続支援B型事業所を探す
1)市区町村の障害福祉窓口または相談支援事業所では、希望条件に見合う就労継続支援B型事業所を紹介してくれます。事業所探しに役立つ情報も入手できます。
2)候補になりそうな就労継続支援B型事業所をインターネットで検索することもできます。
3)候補となる就労継続支援B型事業所が見つかったら、実際に見学してみましょう。一つだけでなく、複数の就労継続支援B型事業所を見学して、いろいろ比べてみることが大切です。
②障害福祉サービス(就労継続支援B型)の支給申請をする
1)市区町村の障害福祉の担当窓口へ支給申請します。
※手続きに関して分からないことがあったら、担当者に何でも聞きましょう。
2)「サービス等利用計画案」を相談支援専門員などが作成して、市区町村に提出します。
3)計画案が承認されると障害福祉サービスの支給が決まり、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
4)相談支援専門員が「サービス等利用計画(本計画)」を作成して市区町村に提出します。
③就労継続支援B型事業所と契約を交わす
・サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行います。
④サービス利用の開始
・いよいよ事業所へ出勤です!
※申請書提出から利用開始までの期間は、1か月半から2か月くらいかかります。そのため、事業所探しと支給申請は並行して行いましょう。
※サービス等利用計画の作成にかかる費用負担はありません。本人が自分で計画を作成すること(セルフプラン)もできます。
まとめ
この記事では、どのような人が就労継続支援B型を利用できるのか、就労継続支援B型の利用者はどのような仕事をやっているのかを解説しました。
また、就労継続支援B型事業所の一日の流れは、勤務形態と障害の状況や程度・体調により、利用者ごとに決められることを説明しました。
最後に、就労継続支援B型を利用するための手続きの流れも解説しました。
「就労継続支援B型って、どんな人がどんな仕事をやって、一日をどう過ごしているのだろう?」などと、就労継続支援B型に興味がおありでしたら、ぜひ一度、ケイエスガードをお訪ねください。
ケイエスガードは神奈川県川崎市にある就労継続支援B型・就労移行支援の事業所です。ケイエスガードでは、得意を活かした就労をサポートするのが得意です!もちろん、利用する方のペースを大切にしています。
興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。電話やLINEでもOKです!